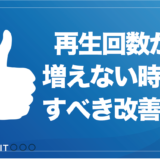「SNSでブランディングできるの?」
「どのSNSでブランディングするのがおすすめ?」
「成功させるコツは?」
と疑問を持っていませんか。
自社でもSNSによるブランディングを始めた方がいいのか、迷っている方も多いはずです。
そこでこの記事では以下のことを解説していきます!
- ブランディングにおけるSNSの活用状況
- 主要SNSの特徴
- SNSでブランディングするメリット
- デメリット
- 失敗しないコツ
- 企業の成功事例
- YouTubeでブランディングするメリット
結論からお伝えすると、ブランディングに最適なのはYouTubeをSNS化して使うことです。
YouTubeをおすすめする理由も詳しく解説しますので、ぜひ参考にご覧ください!
ブランディングにおけるSNSの活用状況

ブランディングの手段として、SNSを使う企業は増加しています。
ここでは、企業の実際の活用状況を解説します。
主要な4つのSNSを使う企業の割合は以下の通りです。
- Facebook:78%
- Twitter:62%
- Instagram:60%
- LINE:31%
なんとFacebookは8割近い企業が利用しているとわかりました。
Facebook以外でも、かなりの割合の企業がSNSを使っています。企業間取引を中心とするBtoBよりも対顧客の取引が多いBtoCの企業で、SNSを積極的に活用しているようです。
ライバル企業に遅れをとる前に自社でもSNSを使い、効果的なブランディングをしていきましょう!
(参考:株式会社ガイアックス「SNSマーケティング最新レポート企業のSNS担当者150名への独自調査」)
主要SNSの特徴

大体数の企業がSNSを使っていることはわかっても、どのサービスを使ったら良いかと迷う方もいるでしょう。
そこでこの章では、日本でよく使われている主要なSNSの特徴を紹介します。
- LINE
それぞれのユーザー層も具体的に解説するので、自社ではどのようなSNSを使うのが効果的か参考にしてみてくださいね。
【ブランディングに使えるSNS1】Facebook
| 日本のユーザー数 | 2,600万人 |
| 利用率 | 32.7% |
| 利用年代のメイン | 30代(世代人口の48.2%) |
Facebookは、世界で最も利用人数が多いSNSで知られています。
Facebookは知り合い同士での交流がメインで、実社会的な雰囲気が特徴的です。実名での登録が推奨されているため、他のSNSと比べると炎上が起きにくいと言われています。
名前以外に学歴や居住地を細かく設定するユーザーが多くいるので、細かいターゲティングによる広告も利用できます。
【ブランディングに使えるSNS2】Twitter
| 日本のユーザー数 | 4,500万人 |
| 利用率 | 38.7% |
| 利用年代のメイン | 20代(世代人口の69.7%) |
Twitterは、LINEについで国内利用者数が多いSNSです。
オープンな交流が盛んで、趣味や属性が合うユーザー同士でやりとりを楽しむ傾向にあります。
Twitterはリアルタイム性に優れているのが特徴です。ブランディング以外にも市場のトレンドを調査したり、ユーザーの意見を吸い上げたりするのに役立つでしょう。
また、拡散能力が高いため、投稿がヒットすれば瞬く間に情報が広まります。人気を集めた投稿がテレビで紹介されるなどの2次効果も期待できますよ。
Twitterでブランディングする攻略方法を知りたい方は、こちらのサイトの記事も役立ちます!
【ブランディングに使えるSNS3】Instagram
| 日本のユーザー数 | 3,300万人 |
| 利用率 | 37.8% |
| 利用年代のメイン | 20代(世代人口の64.0%) |
Instagramは写真投稿がテーマのSNSです。
投稿後24時間で自動的に消えるストーリー機能や、ハッシュタグ検索が印象的です。自社で写真投稿をするだけでなく、インスタグラマーと呼ばれるユーザーとのコラボもブランディングに使えます。
インスタグラマーとは、Instagramの中で一般ユーザーから支持を集める、投稿の影響力が高い人のこと。自社商品をインスタグラマーに紹介してもらうタイアップ手法も、ブランディングに使われています。
コンテンツにこだわりのあるブランディングをしたい企業に、Instagramがおすすめです。
【ブランディングに使えるSNS4】LINE
| 日本のユーザー数 | 8,400万人以上 |
| 利用率 | 86.9% |
| 利用年代のメイン | 20代(世代人口の95.7%) |
LINEは全年代の連絡ツールとして浸透したSNSです。
連絡ツールとして普段使いしている方も多いでしょう。
企業向けの利用メニューはLINE公式アカウント(旧名称:LINE@)と呼ばれています。LINEをブランディングに使うメリットは、自由度の高い情報発信ができること。クーポンを表示したり、個別チャットによる問い合わせ対応ができます。
なお、企業向け機能の本格的な利用には料金がかかります。
SNSをブランディングに使う5つのメリット

SNSをブランディングに使うと、次の5つのメリットが得られます。
- 費用がかからない
- 知識が必要ない
- 情報提供ができる
- 認知拡大ができる
- ファンビジネスができる
それぞれ確認しましょう。
【SNSブランディングのメリット1】費用がかからない
SNSによるブランディングは、無料でスタートできます。費用に余裕のない企業は、安心して活用できますね。
もしアイコンやバナーの制作をプロに依頼しても、工夫次第で高い費用対効果が得られるでしょう。
なお、広告機能を利用するには、有料の場合が多いです。
【SNSブランディングのメリット2】知識が必要ない
SNSは利用に特別な知識は必要ありません。
日常的にSNSを使っている従業員なら、スムーズに情報発信ができるでしょう。
対してサイトやアプリによるブランディングは、管理に高度なスキルが必要です。SNSの選び方次第で、クオリティの高い自社ページを作成できますよ。
【SNSブランディングのメリット3】情報提供ができる
ブランディングのために複合的な情報提供ができます。
多くのSNSは、次のような様々なメディア投稿に対応しているからです。
- テキスト
- 写真
- 動画
- 音声
簡単に投稿できるだけでなく、ユーザーにとっても分かりやすいブランディングが叶うでしょう。
【SNSブランディングのメリット4】認知拡大ができる
SNSを使うと、認知の拡大ができます。
企業に接点のなかったユーザーにも、自社の存在を知らせる機会になるからです。
SNSに投稿した情報はユーザー同士の横の繋がりで、予想を遥かに超える範囲に届きます。SNSで新たなユーザーと出会うきっかけを作り、効率的に潜在顧客を開拓しましょう。
【SNSブランディングのメリット5】ファンビジネスができる
自社のSNSに集まったユーザーを抱え込み、ファンビジネスに活用できます。
SNSは、ユーザーと企業が直接的にコミュニケーションを取れる場だからです。
ファンビジネスとは、企業に好意的なファンを抱え込んだり、さらに育成したりして売り上げの土台にするマーケティング方法です。ロイヤリティの向上や、顧客の質を高める効果が期待できます。
▼ファンビジネスの詳しい方法はこちら▼
 【成功例あり】YouTubeブランディングの5つの極意!機能の使い方も画像つきで解説
【成功例あり】YouTubeブランディングの5つの極意!機能の使い方も画像つきで解説
>>【解説】ファンビジネスは企業こそ検討すべき!3つのメリットや事例を紹介
SNSでブランディングするデメリット

メリットと同時に、SNSならではのデメリットも存在します。
- 効果が出るまで時間がかかる
- 炎上のリスクがある
念の為、一緒に把握しておきましょう。
【SNSブランディングのデメリット1】効果が出るまで時間がかかる
SNSはブランディングの効果が出るまで時間がかかります。
十分なフォロワー(支持数)がいないと、投稿が遠くまで届かないからです。全くのゼロから運営する場合、ユーザーへの知名度が上がるまではコツコツと運用することになるでしょう。
とはいえ、SNSは維持費がかからないので、地道に結果を待つことが可能です。
【SNSブランディングのデメリット2】炎上のリスクがある
SNSは使い方を誤ると炎上するおそれがあります。
インターネットで言うところの炎上とは、批判的なコメントが集中し収集がつかなくなること。例えば、SNSにおける次のような発信は炎上の原因になり得ます。
- 嘘の情報
- 差別的発言
- 悪ふざけ
- 不祥事
ブランディング担当者の間で運用のルールを共有するなど、ユーザーに悪い印象を与えないよう気をつける必要があります。
SNSブランディングで失敗しないコツ5選

せっかくSNSに挑戦するなら、損をせずに運用していきたいですよね。
この章では、SNSブランディングで失敗しないためのコツを5つ解説します。
- ターゲティングを行う
- 更新時間を意識する
- 積極的に交流する
- 適度にキャンペーンを行う
- 投稿に一貫性を持たせる
すぐに対策に移れる内容もありますので、SNS運用の参考にご覧ください。
【SNSブランディングのコツ1】ターゲティングを行う
自社でブランディングするターゲットに合わせて、SNSもターゲティングしていきましょう。
ターゲットを意識した運用の方が、よりユーザーの心に刺さるブランディングができるからです。
例えば、ターゲットに関する以下のような内容を事前に決め、担当者同士で方向性を共有しておくといいでしょう。
- 年齢
- 性別
- 職業
- 興味・関心
- 家族構成
もちろん、ブランディング上すでに決まったターゲットがあるなら、SNSの運営にも活用できます。
ターゲットに狭く深く好まれるSNSブランディングが最適です。
【SNSブランディングのコツ2】更新時間を意識する
SNSの更新時間は意識的に決めましょう。
アクティブユーザーが多い時間にSNSを動かした方が、投稿を目にしてもらえる機会が増えるからです。多くのユーザーーが寝ている深夜に情報発信をしても、反応は期待できません。
例えばTwitterでは、1日の中で2回のピークタイムと、夜のゴールデンタイムが存在します。
- 通勤時間帯の朝7〜8時ごろ
- 昼食時の12時ごろ
- 夜18〜21時までの余暇の時間
(参考:App Ape)
SNSがよく使われる時間帯を狙って活用すると、多くのユーザーに効率的な情報発信ができるでしょう。
【SNSブランディングのコツ3】積極的に交流する
SNSの良さを生かし、積極的にユーザーと交流しましょう。
交流によってユーザーに自社の存在を覚えてもらえたり、好感度を高めたりできるからです。
- 自社に関する話題に反応を示す
- 定形文は避ける
- 「いいね」の機能を活用する
など、工夫できることはたくさんあります。
例えば、ドン・キホーテの公式アカウントでは不良品に対するクチコミに「ダイレクトメールで詳しくお話を伺えませんか」とユーザー1人ひとりに丁寧な返信を行っています。
このような丁寧な交流で、ユーザーからの信頼を育てられますよ。
【SNSブランディングのコツ4】適度にキャンペーンを行う
SNSでキャンペーンを行い、ブランディングに取り入れている企業が多くあります。
SNSにまとまった数のファンがいれば、宣伝費をかけずにキャンペーンができるでしょう。
例えば、次のようなキャンペーンがよく開催されています。
- Twitter:リツイートをしたユーザーの中から抽選でプレゼント
- Instagram:写真投稿でコンテスト開催
- Facebook:投稿に集まったコメントを元にランキング作成
キャンペーンがうまくいけば、企業のブランド価値が広まったり、さらに多くのユーザーを獲得するチャンスになったりしますよ。
【SNSブランディングのコツ5】投稿に一貫性を持たせる
SNSへの投稿は、一貫性を持たせましょう。写真や口調の雰囲気を統一することで、ブランドイメージを固定できるからです。
担当者が複数いる場合はアカウントの雰囲気を損なわないために、特に意識する必要があるでしょう。
運用ルールを決めたり、キャラクターになりきったりするのがおすすめです。
SNSでブランディングに成功した事例

SNSでブランディングを行っている、企業の実例を紹介します。
- ゼスプリ・インターナショナル・ジャパン
- ハーゲンダッツ ジャパン
- 足つぼ Yutaka
それぞれ工夫を参考にしましょう。
【SNSブランディングの事例1】ゼスプリ・インターナショナル・ジャパン
ゼスプリはキウイの生産と販売をしてる会社です。
キウイのキャラクターによる歌とダンスのテレビCMを見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。
テレビCMと同じキウイのキャラクターをTwitterに起用し、ユーザーへの認知度を高めています。
寒い日はグリーンのもふもふな体に限るね☀
こうやって一緒にいると暖かいんだよ♪ pic.twitter.com/xXU1B8ODBR
— ゼスプリキウイ公式 (@zespri_jp) December 11, 2020
【SNSブランディングの事例2】ハーゲンダッツ ジャパン
アイスでお馴染みのハーゲンダッツでは、TwitterとInstagramをブランディングの方向性に合わせて使い分けています。Twitterはキャンペーンやクイズで賑やかな投稿、Instagramはインスタ映え重視の綺麗な写真の投稿が中心です。
それぞれのSNSの得意なことや機能を上手に活用し、ファン層を絞ったブランディングといえます。
\ ハーゲンダッツクイズ /
アイスクリームの主原料であるおいしいミルク作りのために、乳牛が「○ ○ ○ ○ ○」までこだわっています🐄💡
さて、○に入るのは次のうちどれ⁉️
答えは明日 17:00の投稿で👀#ハーゲンダッツ #クイズ— ハーゲンダッツ (@Haagen_Dazs_JP) December 15, 2020
この投稿をInstagramで見る
【SNSブランディングの事例3】足つぼ Yutaka
「足つぼ Yutaka」は、音声もセットで伝えられる動画の特性を生かしたYouTubeチャンネルです。
流行りのASMR(耳で聴いて心地良いと感じさせる動画)で、足ツボの雰囲気を伝えています。
足ツボに興味がなかったASMRファンを上手く取り込み、チャンネル登録者数は10万人を超えました。
予約ページへの誘導も徹底しているため、売り上げに効果的につながるでしょう。
YouTubeならシニア層へのブランディングもできる!

SNSブランディングを考えている方はYouTubeも検討してみましょう。
若者への浸透が進んでいるYouTubeですが、実は高齢者からも支持を集めているからです。70代を中心に、YouTubeを積極的に活用しているというデータが出ています。
(参考:株式会社アスマーク シニアのSNS利用実態・認知購買行動調査)
シニア層による具体的な使い道と、利用割合は以下の3つです。
- 好きなジャンルの情報集め:50%
- 暇つぶし:40%
- 息抜き:36%
高齢者は今までインターネット分野に馴染みがなく、SNSによるブランディングが難しいターゲットでした。
YouTubeを活用すれば、子供から高齢者まで幅広いアプローチができますよ。
YouTubeでブランディングする3つのメリット

YouTubeはターゲットの広さ以外にも、他のSNSにないメリットをたくさん持っています。
ここでは、YouTubeでブランディングするメリットを3つに絞って解説します。
- 効果測定がしやすい
- 濃い情報を伝えられる
- 他のSNSと連携できる
それぞれ確認しておきましょう!
▼YouTubeの動画投稿を始めるメリット・デメリットをたっぷり解説▼
 YouTubeに投稿する7つのメリットとデメリットを徹底解説【個人も企業もやる価値あり】
>>YouTubeに投稿する7つのメリットとデメリットを徹底解説【個人も企業もやる価値あり】
YouTubeに投稿する7つのメリットとデメリットを徹底解説【個人も企業もやる価値あり】
>>YouTubeに投稿する7つのメリットとデメリットを徹底解説【個人も企業もやる価値あり】
【YouTubeブランディングのメリット1】効果測定がしやすい
YouTubeは効果測定がしやすいSNSです。
他のSNSは投稿の効果を調べるツールがついていても、簡易的なものが多く詳しい分析が難しいことがありました。
しかしYouTubeは、かなり詳しいアナリティクスを確認できます。
高度な分析も初心者向けのシンプルなグラフ表示もどちらもできるので、数字を読み取る知識に不安がある方もきっとブランディングに役立てられますよ。
▼アナリティクスで読み取れる内容を解説▼
 【必見】YouTubeのアナリティクスは最低限4つのポイントを押さえよ【読み方丸わかり】
>>【必見】YouTubeのアナリティクスは最低限4つのポイントを押さえよ【読み方丸わかり】
【必見】YouTubeのアナリティクスは最低限4つのポイントを押さえよ【読み方丸わかり】
>>【必見】YouTubeのアナリティクスは最低限4つのポイントを押さえよ【読み方丸わかり】
【YouTubeブランディングのメリット2】濃い情報を伝えられる
YouTubeは動画がメインのサービスなため、濃い情報をユーザーに伝えられます。
視覚、聴覚とあらゆる角度でアプローチできるからです。
他のSNSでは発信できる文字数に制限があったり、動画の長さや画質が決まっていたりします。
YouTubeなら比較的制限が少なく、わかりやすい情報発信ができるでしょう。
【YouTubeブランディングのメリット3】他のSNSと連携できる
YouTubeに投稿した動画は、簡単に他のSNSで紹介できます。
SNSを複合的に利用すれば、より高い拡散効果が狙えますよ。
また、特別な知識なしで自社サイトに動画を埋め込むこともできます。
YouTuberブランディングを始めるなら「ビジネス系YouTubeの学校」

ここまで、SNSブランディングの方法について紹介してきました。今から企業のブランディングを行うならば、YouTubeを掛け合わせるのがおすすめです。とはいえ、動画を作るのはハードルが高いな、と感じる方も多いはず。
YouTubeをやってみたいけれど、何からはじめていいかわからないという方には、当メディアを運営する「もふもふ不動産」の「ビジネス系YouTubeの学校」がおすすめ。チャンネル登録者数26万人を誇るYouTuberもふ社長による、オンライン講座です。
自身がチャンネルを育てたノウハウを惜しみなくお伝えする授業に加え、グループチャットで質問し放題!これからYouTubeを始めたい方は必見です!
[school-button]